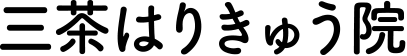お知らせ & コラム NEWS / COLUMN
アレルギー性鼻炎 つらい鼻水・鼻づまりの”根っこ”を断つ!自律神経を整える鍼灸の力

① アレルギー性鼻炎に対する当院の施術
当院では、アレルギー性鼻炎の症状緩和と体質改善を目指し、自律神経と血行促進に重点を置いた鍼灸施術を行います。
鍼灸施術のアプローチ
アレルギー性鼻炎は、主にアレルゲンに対する身体の過剰な反応が原因です。この反応には自律神経の乱れが深く関わっていると考えられています。
-
自律神経の調整
-
首、肩、背中にある自律神経に関わるツボを刺激し、全身のバランスを整えます。免疫機能を整え、鼻粘膜の過敏な反応を抑えることを目指します。
-
症状が強く出る鼻周囲の局所治療と、全身の調整を組み合わせることで、自然治癒力を高め、アレルギー体質の根本的な改善を促します。
-
-
血行促進と炎症の抑制:
-
鼻周囲や顎のツボ、および関連する手足のツボに鍼通電(パルス治療)を施すことで、局所の血行促進を図り、鼻粘膜の充血や腫れ、炎症を抑える効果が期待できます。鼻の通りが良くなり、くしゃみや鼻水といった症状の緩和につながります。
-

② アレルギー性鼻炎の東洋医学的な考え
東洋医学では、アレルギー性鼻炎によるくしゃみ、鼻水、鼻づまりといった症状を「鼻鼽(びきゅう)」や「鼻淵(びえん)」などと捉えます。
特に、「水(すい)」の代謝異常と「肺(はい)」の機能低下、そして「脾(ひ)」・「腎(じん)」の働きが深く関わっていると考えます。
東洋医学的な原因(証立て)
-
水毒(水分の偏在・異常)
-
鼻水や痰といった分泌物は、体内の「水(すい)」が正常に巡っていない「水毒(すいどく)」という病態として捉えられます。水分の代謝を司る「脾(ひ)」や、気の流れを整える「肺(はい)」の機能が低下すると、余分な水分が鼻に停滞し、水っぽい鼻水やくしゃみが生じやすくなります。
-
-
肺気虚(肺の機能低下)
-
東洋医学の「肺」は呼吸器だけでなく、「衛気(えき)」という外敵から体を守るバリア機能(免疫)を司ると考えられています。「肺」の気が不足(肺気虚)すると、バリア機能が低下し、花粉などの外邪(外からの病因)に過敏に反応しやすくなります。
-
-
脾腎両虚(消化器・生命力の低下)
-
体を温め、水分の代謝と免疫の土台を支える「脾(ひ)」や「腎(じん)」の機能がもともと弱い体質の場合、冷えや過労によってさらに機能が落ち、アレルギー症状が出やすくなります。これは体質の根本的な原因とされます。
-
主に使用するツボ
東洋医学では、標治(症状を抑えること)と本治(体質を改善すること)の両面からツボを選びます。
-
標治(局所・症状緩和)
-
迎香(げいこう):鼻の通りを良くする特効穴。鼻の付け根の両脇。
-
印堂(いんどう):眉間。鼻づまりや精神的な安定にも。
-
-
本治(体質改善・免疫調整):
-
合谷(ごうこく):手の甲、万能のツボ。免疫調整や自律神経調整に。
-
足三里(あしさんり):膝下。消化器系「脾」の機能を高め、体力をつける。
-
大椎(だいつい):首の付け根。免疫機能の調整によく用いられる。
-

③ アレルギー性鼻炎とは?
アレルギー性鼻炎は、空気中の特定のアレルゲン(抗原)を吸い込むことで、鼻の粘膜でアレルギー反応が起こり、くしゃみ、鼻水、鼻づまりなどの症状が慢性的に現れる病気です。
一般的な医学的症状と分類
発生メカニズム
くしゃみ
鼻の粘膜の神経が刺激され、異物を体外に排出する防御反応。
鼻水
異物を洗い流すための防御反応。主にサラサラした水様性。
鼻詰まり
鼻粘膜の血管が拡張し、粘膜が腫れる(浮腫)ことで起こる。空気の通り道が狭くなる。
アレルギー性鼻炎は、原因となるアレルゲンの種類と症状が現れる時期によって、主に以下の2つに分類されます。
-
季節性アレルギー性鼻炎:特定の季節にのみ症状が現れるもの。
-
代表例:花粉症(スギ、ヒノキ、イネ科、ブタクサ、ヨモギなど)
-
-
通年性アレルギー性鼻炎:年間を通して症状が現れるもの。
-
代表例:ダニ(ハウスダストの主成分)、ペットのフケ、カビなど
-
疫学
アレルギー性鼻炎は非常に有病率の高い病気で、近年の調査では国民の約2人に1人が罹患しているとも言われています。特にスギ花粉症の患者数は年々増加傾向にあり、生活の質(QOL)を大きく低下させる要因となっています。
④ アレルギー性鼻炎の原因
アレルギー性鼻炎は、本来無害な物質(アレルゲン)に対して、体の免疫システムが過剰に反応することで起こります。この反応の引き金となる医学的な原因は以下の通りです。
1. アレルゲン(抗原)
アレルギー反応を引き起こす原因物質で、主に空気中に浮遊しています。
-
季節性:花粉(スギ、ヒノキ、ブタクサなど)
-
通年性:ダニ(ハウスダストの主成分)、カビ、ペットの毛やフケ
2. 免疫システムの過剰反応
-
IgE抗体の産生
-
アレルゲンが鼻の粘膜から体内に入ると、免疫システムがそれを異物と認識し、IgE抗体という特殊な抗体を作り出します。
-
-
肥満細胞との結合
-
IgE抗体は、鼻粘膜の表面にある肥満細胞(マスト細胞)に張り付きます。
-
-
化学伝達物質の放出
-
再びアレルゲンが侵入すると、肥満細胞に結合したIgE抗体とアレルゲンが反応し、細胞からヒスタミンやロイコトリエンなどの化学伝達物質が放出されます。
-
-
症状の発現
-
これらの化学伝達物質が、鼻の神経や血管を刺激し、くしゃみ、鼻水、鼻づまりといったアレルギー症状を引き起こします。
-
ヒスタミン:くしゃみ、鼻水に関与。
-
ロイコトリエン:血管を拡張させ、鼻粘膜の腫れ(鼻づまり)に関与。
-
-
3. 体質的な要因
-
遺伝的要因:アレルギー体質は遺伝的な影響を受けることがあります。
-
環境要因:食生活の欧米化、衛生環境の変化、ストレスなど、様々な要因が複合的に関与し、自律神経のバランスの乱れや免疫機能の過敏性を高めていると考えられています。
⑤ アレルギー性鼻炎の養生法とセルフケア方法
アレルギー性鼻炎の症状を和らげるためには、日常生活での養生法とセルフケアが非常に重要です。
1. 身体を冷やさない 温活
東洋医学では、冷えは水分の停滞(水毒)を悪化させ、鼻炎を招く大きな原因と考えます。
足元を温める:靴下やレッグウォーマーで下半身を冷やさないようにしましょう。足湯は血行を良くし、鼻の粘膜の温度を上げる効果も期待できます。
首周りをガード:首・肩の冷えは自律神経の緊張を招きやすいため、マフラーやタートルネックなどで温めます。
食事の工夫:体を温める食材(生姜、ネギ、カボチャ、根菜類など)を積極的に摂りましょう。冷たい飲み物や生野菜、寒性の果物(バナナ、スイカなど)の摂りすぎには注意が必要です。
2. ツボ押しセルフケア
入浴後など、体が温まった状態で行うとより効果的です。
迎香(げいこう)
鼻の付け根の両脇、小鼻の横
人差し指で優しく、少し上に向かって押し込むように3秒押し、3秒離すを数回繰り返す。
鼻の通りを良くする、鼻水の分泌を抑える。
合谷(ごうこく)
手の甲、親指と人差し指の骨が交わる手前のへこみ
反対側の親指で、骨に向かって少し痛気持ちいい程度の強さで押す・もむを繰り返す。
全身の免疫調整、くしゃみや目のかゆみ緩和。
印堂(いんどう)
左右の眉毛の中央(眉間)
親指で優しく、額の中心に向かって押す。
鼻づまり緩和、リラックス効果(自律神経調整)。
3. 加湿
入浴・加湿:入浴中の湯気や加湿器で鼻腔を潤すことは、鼻粘膜の乾燥を防ぎ、鼻詰まりの緩和につながります。
アレルギー性鼻炎は、くしゃみや鼻水などの不快感だけでなく、集中力や睡眠の質を低下させ、仕事や勉強のパフォーマンスにも影響します。
体質を改善して、症状の軽減を目指しましょう。
アレルギー性鼻炎でお困りの方、
三茶はりきゅう院にお気軽にご相談ください。
東洋医学の視点で、症状に合わせたオーダーメイドの施術であなたのアレルギー性鼻炎を全力でサポート致します。
まずはお電話またはこちらからご連絡ください。
グループ院のご紹介
東京α鍼灸院:中目黒駅
渋谷α鍼灸院:渋谷駅
吉祥寺αはりきゅう院:吉祥寺駅
高田馬場はりきゅう院:高田馬場駅
【執筆者】
三茶はりきゅう院
鍼灸師 平坂
東急田園都市線.世田谷線「三軒茶屋駅」徒歩3分
平日20:30まで受付、土日祝も営業
完全個室の施術室
ご予約はこちらから
\相談だけでも大丈夫ですのでお気軽に/
はじめての方も安心の返金保証制度をご用意しております。
たった一度のご来院でも、我々の専門知識と確かな技術で
お客様のお悩みの症状に対する概念を、きっと変えられると思ってます。
是非一度お気軽にご相談ください。