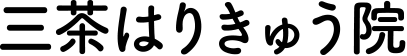お知らせ & コラム NEWS / COLUMN
上咽頭炎

鼻づまりや粘着性の鼻水が喉に流れる後鼻漏など、風邪をきっかけに喉の奥に炎症が残る事があります。
その症状は上咽頭炎かもしれません。
上咽頭炎に対する当院の施術
鼻の不快な症状が睡眠に影響を及ぼす事も多々あります。辛い日が続く事で自律神経系が上手く働かず、交感神経優位や副交感神経優位、どちらかに偏りがあると入眠しずらくなったり、沢山寝ても朝すっきり起きれない状態が続いたりします。
まずは全身の筋緊張緩和を目的に身体にある穴を使い鍼やお灸で治療を行っていきます。
身体に炎症がある=身体に熱がこもっている状態、と考え身体全体に熱を循環させる必要があると考えます。
耳鼻科の症状でお困りの方は首肩こりがある方が多く、喉や鼻の炎症が循環しにくくなる事で慢性的に症状が続いてしまう可能性があります。
まずは首や肩の固さ、背中の張りを確認し、鍼とお灸を使い緩めていきます。

上咽頭炎の東洋医学的な考え
五臓六腑の「肝」は疏泄を主る、生理機能があり全身の気機を調節します。この疏泄機能が滞り流れが悪くなると「肝気鬱結」という状態になります。
肝血が鬱結すると血流も障害されやすくなります。血流が障害される事で血瘀となり、痰飲などの病理産物を形成します。
痰飲とは「肺脾腎」3つの機能失調により水液代謝に障害がおこり生じる病理産物です。
粘稠なものは「痰」水様なものは「飲」になり、合わせて痰飲となります。形ある痰は炎症がある時に出る痰、形ないものは身体を流れる経絡に停滞すると考え、梅核気(西洋医学的にはヒステリー球)などは痰邪によりおこると考えられています。

上咽頭炎の方へセルフケア
症状が強い時はなるべく避けた方が良い食材
1.脂身の肉類
2.スイーツ類
3.香辛料(辛いスパイス系)
4.アルコール
上咽頭はどこにある?
上咽頭は外鼻(鼻の入り口)から鼻腔、後鼻孔を通り、その一番奥側で喉の一部です。
上咽頭の周辺には沢山毛細血管も集まっていて冷たい空気を温める役割と、粘液も分泌されているので湿り気があり、乾燥した外気を潤す役割もあります。
上咽頭炎の原因
身体には口や鼻から侵入したウイルスや細菌が体内に入り込まないように備わっているのが「免疫」という防御システムです。
人は生きていく為に呼吸が必要になり、喉や鼻は常にウイルスや細菌に晒されています。喉や鼻に違和感がなくても免疫細胞は常に働き続けていて、常に軽い炎症が起きているとも言えます。
ウイルスや細菌と戦っている免疫機能がしっかりしていれは炎症はおさまります。
炎症がおさまりにきらずに残ってしまうと慢性的な上咽頭炎という事になり、鼻水、鼻づまり、喉が痛い、頭痛、肩こり、首こり、不眠、めまい、胃もたれ、身体のだるさとして現れます。

上咽頭炎でお困りの方、
三茶はりきゅう院にお気軽にご相談ください。
東洋医学の視点で、症状に合わせたオーダーメイドの施術であなたの上咽頭炎を全力でサポート致します。
まずはお電話またはこちらからご連絡ください。
【グループ院の紹介】
東京α鍼灸院:中目黒駅
渋谷α鍼灸院:渋谷駅
吉祥寺αはりきゅう院:吉祥寺駅
高田馬場はりきゅう院:高田馬場駅
【執筆者】
三茶はりきゅう院
鍼灸師 内田
東急田園都市線・世田谷線「三軒茶屋駅」徒歩3分
平日20:30まで受付、土日祝も営業
完全個室の施術室
ご予約はこちらから
\相談だけでも大丈夫ですのでお気軽に/
はじめての方も安心の返金保証制度をご用意しております。
たった一度のご来院でも、我々の専門知識と確かな技術で
お客様のお悩みの症状に対する概念を、きっと変えられると思ってます。
是非一度お気軽にご相談ください。