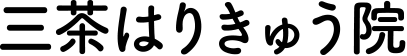お知らせ & コラム NEWS / COLUMN
「味がしない」味覚障害について

「最近、食べ物の味が薄く感じる」「何を食べても美味しくない」
そんな違和感を覚えたことはありませんか?
味覚は、体調の変化をいち早く察知する「感覚器」としての役割があり、体に必要な味はより美味しく感じます。
例えば夏場に熱くなった体にとって、体を冷やす作用のある苦味(ビールなど)はより美味しく感じます。
近年では、新型コロナウイルス感染症の影響により「味がしなくなった」という経験をされた方も多く、一時的な問題と思われがちですが、実は味覚障害にはさまざまな原因が存在します。
単なる加齢や風邪の後遺症にとどまらず、ストレスや自律神経の乱れ、栄養不足、薬の副作用、そして内臓機能の低下など、多くの身体的・心理的背景が複雑に関わっています。
味覚障害とは何か?
──分類と原因の多様性
味覚障害とは、味を感じる能力が低下したり、異常をきたす状態の総称です。代表的な分類は下記のようなものがあります。
亜鉛欠乏性味覚障害
味蕾(味を感じる細胞)の新陳代謝には亜鉛が不可欠であり、これが不足すると味覚が低下します。高齢者、偏食傾向、慢性的な胃腸疾患を持つ人に多く見られます。
感染後味覚障害(ウイルス性感染後)
インフルエンザや新型コロナウイルス感染後に発症するケースも増えています。ウイルスが嗅神経・味神経に影響を及ぼすことで、一時的または長期的に味覚異常が生じます。
加齢性味覚障害
年齢とともに味蕾の数が減少し、味を感じにくくなります。また、唾液分泌の減少や内臓機能の低下も一因とされています。
味覚障害がもたらす日常生活への影響
味覚は、単に「おいしい」「まずい」と感じるだけの感覚ではありません。食事を通じて五感を満たし、心と体に安らぎを与える重要な役割を担っています。
食事の楽しみの喪失と栄養不良
味が感じられない、すべてが同じ味に思える、苦味や異臭を感じる──こうした変化は、食欲そのものを低下させます。
結果として偏食や食事量の減少、栄養状態の悪化を招くことも少なくありません。
特に高齢者では、低栄養や体力低下につながるため注意が必要です。
情緒やメンタルヘルスへの影響
家族や友人と食べる楽しさが減ると、次第に気分の落ち込みや無気力感へとつながっていきます。実際、味覚障害の方の中には、「うつっぽくなった」「何事にも興味が持てない」といった心理的症状を併発するケースもあります。
東洋医学からみた味覚障害 〜「脾」「腎」との関係〜
「味覚」は、体全体の気・血・津液(しんえき)のバランスと五臓の働きと密接に関わっていると考えます。とくに味覚に関連するとされるのが「脾(ひ)」「腎(じん)」二つの臓です。

脾 ── 味覚の土台を支える臓
「脾」は東洋医学において、消化吸収と、栄養運搬の中心的役割を担う臓腑であり、味覚とのつながりも深いとされます。
食べ過ぎや疲労、思い悩みが続くと脾の働きが低下し、味覚がぼんやりと曇ったようになることがあります。
腎 ── 加齢や慢性疾患と関わる味覚低下の要因
「腎」は生命エネルギーの貯蔵庫であり、加齢や慢性の病気、過労による衰えが現れやすい臓です。
味覚障害の中でも、「年齢とともに味がわからなくなってきた」「最近、何を食べてもおいしく感じない」といった症状は、腎虚の兆候と考えられます。耳鳴りや冷え、倦怠感を伴うこともあります。
「気・血・津液」の不足と味覚の鈍化
さらに東洋医学では、「味覚異常」は単に臓腑の不調だけでなく、体内を巡る気(エネルギー)、血(栄養)、津液(水分)の不足や偏在とも関係すると考えます。
気虚(ききょ)…全身のエネルギー不足により、味を感じる力そのものが低下する
血虚(けっきょ)…栄養不足により、味蕾や舌の感覚が鈍る
津液不足(しんえきぶそく)…口が乾燥して味が感じづらくなる
これらの虚弱状態が複合的に関わり、味覚障害という症状として現れるのです。
このように東洋医学では、「味覚障害=舌の問題」とは捉えず、全身のエネルギーバランスや臓腑の調和の乱れとしてアプローチしていきます。

味覚障害への鍼灸施術
脾胃を補い、味覚の土台を立て直す
味覚をつかさどる土台となる「脾胃(消化吸収系)」の虚弱がみられる場合、体内の気血の生成がうまくいかず、味覚を感じる力が低下すると考えられます。こうしたケースでは、以下のようなツボを中心に施術を行います。
・中脘(ちゅうかん):胃の働きを整える代表的なツボ
・足三里(あしさんり):胃腸を強くし、全身の気血を補う
・脾兪(ひゆ)・胃兪(いゆ):脾胃の機能を高める背部兪穴
これらのツボに鍼や灸で刺激を与え、消化機能と気血の巡りを改善していきます。

ストレスや自律神経の乱れが背景にある場合
心理的ストレスや自律神経のアンバランスが影響している味覚障害には、「気の巡り(気滞)」を解きほぐすような施術を行います。
・太衝(たいしょう):肝気の滞りを解消し、精神的緊張を和らげる
・内関(ないかん):自律神経の調整や胸のつかえを解消するツボ
・神門(しんもん):心を安定させ、過敏な神経反応を和らげる
これらは特に、心因性の味覚障害や、不眠・動悸・胸苦しさを伴うことがあります。

味覚回復に関わる舌や顔面周囲のツボ
直接的に味覚をつかさどる「舌」へのアプローチとして、顔面部のツボを活用することもあります。これは特に、ウイルス感染後の味覚障害や、局所的な神経の感覚低下がみられる方に対して行います。
・地倉(ちそう)、迎香(げいこう):顔面部の血流を改善し、感覚神経の働きを促す
「西洋医学 × 東洋医学」
一般的な医療機関では、味覚障害の主な原因として「亜鉛欠乏」「薬剤の副作用」「口腔疾患」などが考慮され、それに応じて以下のような治療が行われます。
・亜鉛製剤の処方(例:ポラプレジンクなど)
・服用中の薬の調整
・口腔内環境の改善指導
これらは、明確な原因が特定できた場合に非常に有効ですが、一方で「検査で異常なし」「原因不明」「投薬を続けても変化がない」というケースでは、治療が行き詰まることも少なくありません。
鍼灸による治療:全身を見て「回復力」そのものを高める
鍼灸は、体全体の気血の流れや内臓のバランス、自律神経の調和に働きかけることを目的とした治療法です。
味覚障害そのものを“局所的な感覚の問題”と見るのではなく、「なぜその症状が今、あなたの体に現れたのか?」という背景(体質・ストレス・体力低下など)に着目します。
鍼灸は、特に以下のようなケースで適しています。
☑️検査では異常が見つからないが、明らかに味覚の変化を感じている
☑️ウイルス感染後やストレス後など、はっきりしたきっかけがある
☑️慢性的に体調を崩しやすく、疲れや冷えも感じている
☑️病院治療を受けているが改善に乏しい
西洋医学の「不足を補う治療」と、東洋医学の「巡らせ、整える治療」は、本来相反するものではなく生きてるよ補完的な関係にあります。
たとえば、亜鉛製剤によって味蕾の再生を促しつつ、鍼灸によって舌や顔面部の血流を改善し、自律神経の緊張を緩和することで、回復のスピードや体全体の調子を底上げすることが期待されます。
また、鍼灸は副作用がほとんどなく、自然な回復力を引き出すため、長期間の服薬に抵抗がある方や、体質的に薬が合わない方にとって有効な選択肢となりうる治療法です。
「味を取り戻すこと」は、単に味覚の回復だけではありません。日常の喜びや、生きる力を取り戻すことそのものです。
鍼灸には、そのための道を照らす力があります。
味覚障害でお悩みでしたら三茶はりきゅう院へご相談ください。
当院にはこれまで味覚障害の方が多く来院されております。
味覚障害でお困りでしたら、お電話かこちらからお気軽にご連絡下さい。
【グループ院の紹介】
東京α鍼灸院:中目黒駅
渋谷α鍼灸院:渋谷駅
吉祥寺αはりきゅう院:吉祥寺駅
高田馬場はりきゅう院:高田馬場駅
【執筆者】
三茶はりきゅう院
鍼灸師 内田
東急田園都市線・世田谷線「三軒茶屋駅」徒歩3分
平日20:30まで受付、土日祝も営業
完全個室の施術室
ご予約はこちらから
\相談だけでも大丈夫ですのでお気軽に/
はじめての方も安心の返金保証制度をご用意しております。
たった一度のご来院でも、我々の専門知識と確かな技術で
お客様のお悩みの症状に対する概念を、きっと変えられると思ってます。
是非一度お気軽にご相談ください。